保活をやろうとして、調べていると、用語が多かったり似たような単語が多かったりで混乱しませんか?
私は、混乱した方です(^◇^;)1号認定2号認定3号認定があるだけでなく、新○号まででてきて…。
同じように混乱している方に、施設等利用給付認定って何?新1号認定、新2号認定、新3号認定がそれぞれ何のか、何歳が対象なのかできるだけ分かりやすく解説したいと思います。
- 1号認定で預かり保育を受ける方
- 認可外保育施設を利用する方
- 私学助成の幼稚園等を利用する方
ミールキットならヨシケイがおすすめ!
こんな疑問やお悩みありませんか?
子育てや育児が忙しくて栄養バランスを考えた食事を取れていない…
共働きで忙しくてレトルトやスーパーの惣菜で済ませることが多い…
離乳食や幼児食を別で作るのが手間で…何か良い方法ないのかな?
そんな時には、簡単調理のミールキットを自宅まで届けてくれるヨシケイがおすすめです。
「食材宅配サービスって興味あるけど、使ったことなくて…」という方も多いかもしれません。食材宅配サービスを使うことで、献立を考えたり買い物で重い荷物を持ったりといった家事の負担が減り、食材も余らすことなく食費を抑えられたという方もいます。さらに、時短調理ができたり、離乳食や幼児食の取り分けにも使えたりします。
- ヨシケイの口コミ
-
実は今、ヨシケイでは、50%を超える特別割引価格で週5日間ミールキットをお試しをすることができます。
5日間お試ししてみたヨシケイのミールキット





幼児や乳児など小さいお子さんがいて、簡単調理のミールキットが気になる方は、チェックしてみてください。
ヨシケイのお試しセットはこんな人におすすめ!
- 10分〜作れる簡単時短調理で家事の負担を減らしたい
- 配達料無料で良心的な価格のミールキットをお試ししてみたい
- 栄養士監修の健康的な食事を食べたい
- 乳幼児の離乳食や幼児食の取り分けができるサービスを使ってみたい
ヨシケイのプチママをお試ししてみた口コミを詳しく知りたい方は、こちらのサイトを参考にしてみてください。
施設等利用給付認定って何?
2号認定と新2号認定の違いをみていくために、まずは、新2号認定の認定区分が含まれる施設等利用給付認定について見ていきたいと思います。
施設等利用給付認定とは
施設等利用給付認定とは『教育・保育給付認定』の対象外の保育施設の保育料を無償にするための認定です。
つまり「 教育・保育給付認定(1号認定・2号認定・3号認定)を受けて保育料が無償化となった人以外の人達も公平に無償化しますよ 」という認定です。
そのため、施設等利用給付認定のお話は、教育・保育給付認定を受けている方の中で1号認定の方以外は関係が薄い話にはなってしまいます。1号認定の方は預かり保育の無償化を受けるためには施設等利用給付認定で新2号認定を受ける必要があるからです。
ただ、認可外保育施設に通う場合にはとても関係があるお話です。なぜなら、認可外保育施設で無償化を受けるためには、この施設等利用給付認定が必要になるからです。
教育・保育給付認定については、下の記事を参考にしてください。
無償化の対象となる利用料
具体的に、施設等利用給付認定によってどの利用料が無償化の対象となるのか気になるところですよね。
対象となる利用料は次の2つです。
- ⚪︎基本の保育料
-
基本保育料とも呼ばれます。施設を利用するのに最低限支払う必要がある保育料のことです。
※スクールバス代などの実費負担分や施設独自の追加負担費用などは含まれません。 - ⚪︎預かり保育などの利用料
-
預かり保育料とも呼ばれます。通常の保育時間を超える預かり保育で発生する利用料のことです。
無償化の対象となる施設
次に、どの施設が施設等利用給付認定で無償化の対象となるかを見ていきたいと思います。
施設等利用給付認定の認定区分によっても異なりますが、下記の施設が施設等利用給付認定の対象となります。
基本保育料のみが無償化対象となる施設です。
- 国立大学附属幼稚園
- 特別支援学校幼稚部
基本保育料部分が教育・保育給付認定の無償化対象となている新制度の幼稚園や認定こども園でも、預かり保育料が施設等利用給付認定で無償化対象となります。
つまり、施設等利用給付認定を受けることができれば、基本保育料と合わせて預かり保育料の無償化も受けることができるのです。
- 新制度の幼稚園
- 認定こども園
※新制度の幼稚園と認定こども園の基本保育料については、教育・保育給付認定(1号認定)で無料になります。
新制度の幼稚園や認定子ども園の預かり保育は、施設等利用給付認定で無償化の対象になるんだね
- 私学助成の幼稚園等
- 認可外保育施設(ベビーホテル、事業所内保育施設、ベビーシッターなど)
- 一時保育
- 預かり保育
- 病児・病後児保育
- ファミリー・サポート・センター事業
※私学助成の幼稚園とは、子育て支援新制度に移行していない園で各園で入園料や保育料を決定している園で、保育料は保護者負担になります。また、保護者は、施設等利用給付認定により月額25,700円までを上限に保育料の補助を受けることができます。対して、子育て支援新制度に移行している園(新制度の幼稚園)は幼児教育無償化により保育料(利用者負担額)は0円ですが、園によっては、特定負担額や実費の負担が生じる場合があります。
認可外保育施設なども、施設等利用給付認定で無償化の対象になるんだね
認可外保育施設については、下の記事を参考にしてください。
教育・保育認定と施設等利用給付認定の違い
内閣府が出している『 施設等利用給付認定の実務フロー 』で、教育・保育認定と施設等利用給付認定の違いについて書かれています。
違いは、大きく3つあります。
①年齢の基準
教育・保育認定と施設等利用給付認定では、認定の要件となる年齢の基準が異なります。
同じ3歳が境目に境目になっていますが、下のように若干基準が異なります。
- ⚫︎ 教育・保育認定
-
3号認定は満3歳未満の子ども
2号認定は満3歳以上の子ども - ⚫︎ 施設等利用給付認定
-
新3号認定は満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
新2号認定は満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども
※ 施設等利用給付の新3号認定は、保育の必要性以外にも住民税非課税世帯の子どもであることも要件とされています。
②保育必要量認定
保育必要量(保育標準時間・保育短時間)の認定があるかないかも異なります。
- 教育・保育認定 ⇨ 保育必要量(保育標準時間・保育短時間)の認定が有る
- 施設等利用給付認定 ⇨ 保育必要量の認定は無い
③支給認定証交付
支給認定証が交付されるかどうかも異なります。
- 教育・保育認定 ⇨ 支給認定証を保護者の申請に応じて交付する仕組み
- 施設等利用給付認定 ⇨ 支給認定証の交付はせず、認定内容を保護者に通知する仕組み
施設等利用給付認定を受けられない人
既に同様の給付認定を受けて無償化の対象となっている人は、重複してしまうので施設等利用給付認定を受けられません。
施設等利用給付認定を受けられないケースは下記の通りです。
- 教育・保育認定で2号認定または3号認定を受けていて給付の支給を受けている場合
- 企業主導型保育事業を利用している場合
2号認定と新2号認定の違い
2号認定と新2号認定はどのように違うのでしょうか。
次の3点が大きく異なります。違いは①対象施設 ②対象利用料 ③年齢の基準です。
- ⚫︎認定保育所・認定こども園に通う子ども保育必要量を認定するとともに保育料を無償化する位置付け
-
①対象施設:認可保育所、認定こども園
②対象利用料:保育料全般(基本保育料と預かり保育料)
③年齢の基準:満3歳以上
- ⚫︎幼稚園に通う子どもの預かり保育料を無償化する位置付け
-
①対象施設:幼稚園、認定こども園(1号認定)、私学助成幼稚園等
②対象利用料:預かり保育料
③年齢の基準:満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども
- ⚫︎認可外保育施設等に通う子どもの保育料全般(基本保育料と保育料の両方)を無償化する位置付け
-
①対象施設:認可外保育施設等
②対象利用料:保育料全般(基本保育料と保育料の両方)
③年齢の基準:満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども
同じ教育・保育給付認定の中でも2号認定や3号認定を受けている方は、施設等給付認定を受けることができませんが、1号認定を受けている方は、1号認定 + 新2号認定というようなかたちの認定の受け方が可能です。
施設等利用給付認定の認定区分(新1号認定、新2号認定、新3号認定)
施設等利用給付認定の各認定区分について詳しくみていきたいと思います。
それぞれ新1号認定、新2号認定、新3号認定があります。
新1号認定
- 満3歳以上の子どもが対象
- 私学助成の幼稚園等(国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部も含む)を利用する方が対象
- 基本保育料のみが無償化の対象
- 無償化の範囲は月額上限25,700円
※無償化とは呼ばれていますが、無料で費用が一切かからないということではないので注意が必要です。
新2号認定
- 3歳〜5歳児クラス(小学校就学前まで)の子どもが対象
- 新制度の幼稚園や認定こども園、認可外保育施設等を利用する方が対象
- 『 保育の必要性の認定 』が必要
- 新制度の幼稚園や認定こども園を利用する方は預かり保育料のみが無償化対象
※上記の場合の預かり保育料に対する無償化の範囲は月額上限11,300円 - 認可外保育施設等を利用する方は保育料全般(基本保育料と預かり保育料)が無償化対象
※上記の場合の保育料全般に対する無償化の範囲は月額上限37,000円
新3号認定
- 0歳〜2歳児クラスの子どもが対象
- 住民税非課税世帯の家庭が対象
- 新制度の幼稚園、認定こども園、私学助成の幼稚園等を利用する満3歳児の方は預かり保育料のみが無償化対象
※上記の場合の預かり保育料に対する無償化の範囲は月額上限16,300円 - 認可外保育施設等を利用する方で0歳〜2歳児クラスの方は保育料全般が無償化の対象
※上記の場合の無償化の範囲は月額上限42,000円
※満3歳児は3歳になった日から最初の3月31日までにある子どもを指しています。
いかがでしたでしょうか。役に立てば嬉しいです。

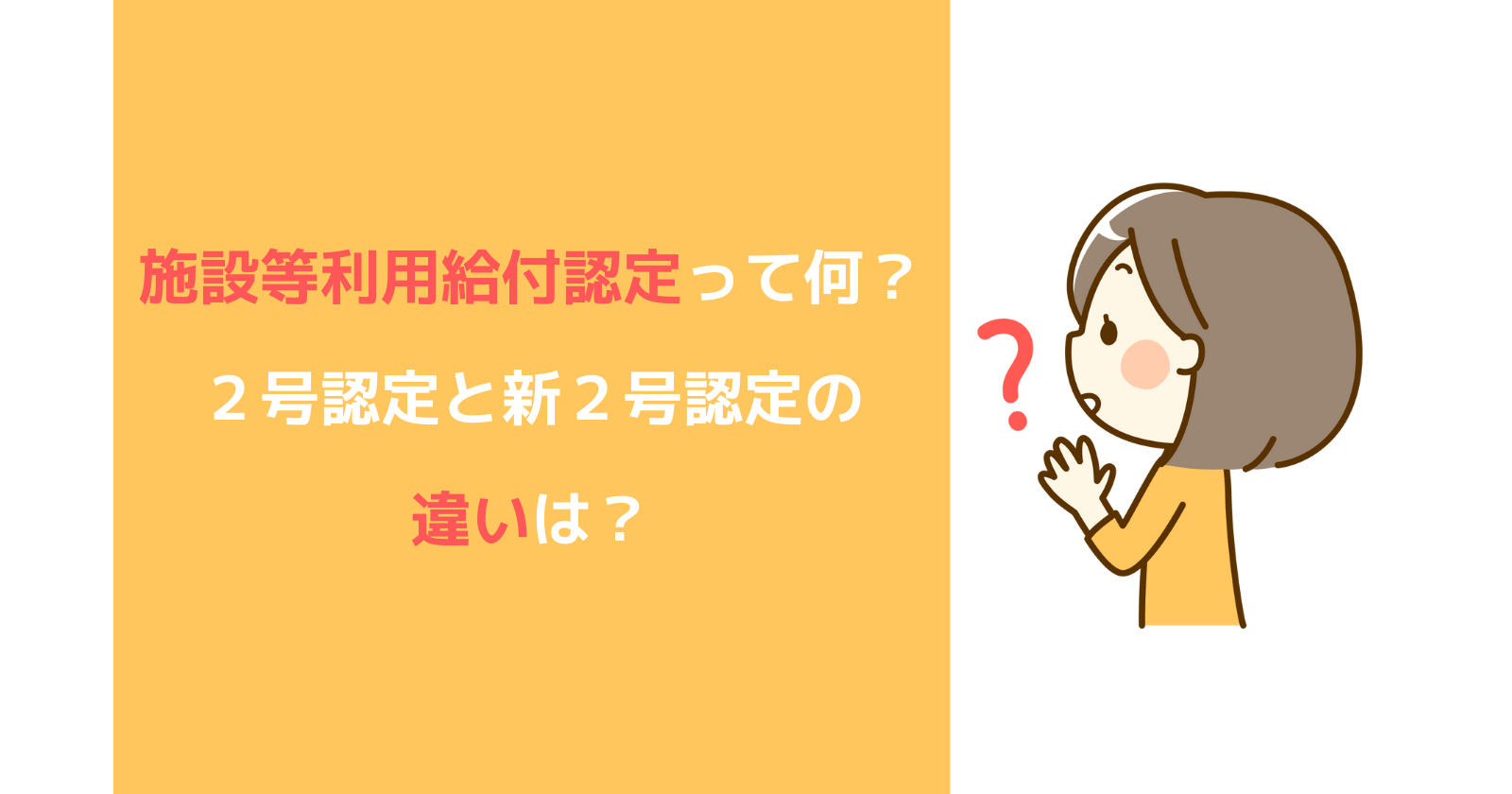
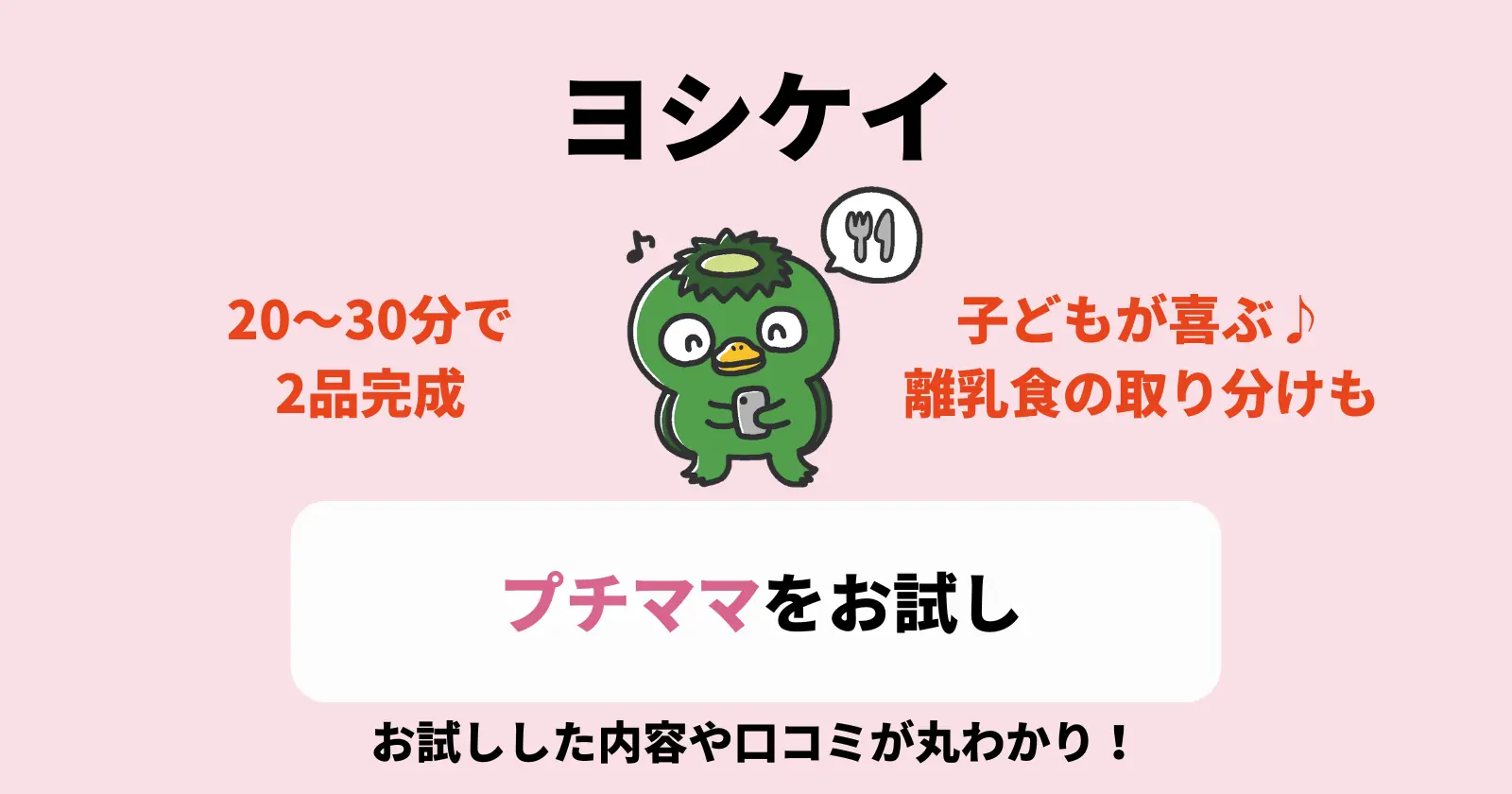


コメント