添い乳で寝ている合間に授乳をすると虫歯になるという話を聞いたことがあるでしょうか?
母乳育児で子どもを育てている方にとっては、子どもが寝ている間、特に夜間の添い乳がなかなか止められないという方も多いかもしれません。
我が家では、乳児期からずっと添い乳で寝かしつけを行っていましたが、我が子は虫歯になりませんでした。ですが、1歳6ヶ月検診(1歳半検診)で歯科医の先生から虫歯を考えると添い乳は止めた方が良いとアドバイスを受けました。
そこで、添い乳をやめるために悪戦苦闘して寝る前の添い乳をやめました、ただ、夜明け前の朝方などには2歳を過ぎた今も授乳を続けています。それでも、現在我が子は虫歯にはなっていません。
この記事では、添い乳でも虫歯にならなかった我が家の体験談とその方法をご紹介したいと思います。
添い乳って何?
添い乳とはどういった授乳方法なのでしょうか。添い乳のメリットとデメリットについても見ていきたいと思います。
添い乳とは
添い乳とは、ママが横になりながら、横並びの赤ちゃんに授乳をすることです。
夜間など添い乳をしながら寝てしまうママもいて、寝ながら行う授乳と勘違いしてしまうかもしれませんが、決してそのような授乳方法を指す訳ではないようです。
日中起きている時間の多くは「横抱き」や「縦抱き」、「フットボール抱き」などの抱き方で授乳するママがほとんどなのではないでしょうか。添い乳は主に寝かしつけるときに行われる授乳方法で、楽な姿勢で授乳ができ、夜間の授乳もママが起き上がることなく授乳することができるため、多用されることが多いようです。
具体的には、横向きに寝転がり乳房の正面に赤ちゃんの顔が来るように、タオルなどを敷いて頭が高くなるように寝かせ、できるだけ赤ちゃんの顔に乳房を近づけ授乳をします。
この時、自分の体と赤ちゃんがぴったりと密着していることがポイントのようです。
密着していないと赤ちゃんが乳首をうまくくわえられなず、赤ちゃんの頭を押し付けないようにしながら、自分から赤ちゃんに近づくようにして授乳をします。
首がしっかりしてくる生後2~3ヶ月になると楽にできるようになるようです。
添い乳のメリットとデメリット
起き上がることなく楽な体勢で授乳ができるため、ママにとっては嬉しい授乳方法である添い乳ですが、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
添い乳には下記のようなメリット・デメリットがあるとされています。
・楽な姿勢のため、ママも赤ちゃんもリラックスしやすい
・赤ちゃんはそのままの体勢で眠れるため、寝かしつけがしやすい
・赤ちゃんが窒息し事故に繋がるリスクがある
・赤ちゃんが中耳炎になる可能性がある
・乳歯が生え離乳食を食べ始めた赤ちゃんには、虫歯リスクが高くなる
・同じ体勢で授乳を続けていると、ママが白斑や乳腺炎になりやすくなる
添い乳で虫歯になるの?
添い乳で虫歯になるって本当なの?
諸説あるようですが、添い乳で虫歯になる可能性が高くなると言われています。
ただこれは、あくまで、虫歯になる可能性が高くなるのであって、必ずしも虫歯になるわけではありません。
では、なぜ添い乳をすると虫歯リスクが高くなるのでしょうか?
添い乳で虫歯リスクが高くなる理由
添い乳で虫歯リスクが高くなる原因は、口の中に残っているプラーク(歯垢)だと言われています。
虫歯になる可能性が高くなるメカニズムはこうです。
赤ちゃんの寝かしつけに添い乳をしたり、添い乳をして赤ちゃんを寝かしつけしたりすることが多いですよね?
口の中にプラークが残ったまま寝てしまうと、就寝時に母乳の影響もあって唾液の分泌量が少なくなり、虫歯になりやすい状態が作られてしまうということのようです。
添い乳で虫歯リスクが高まるメカニズム
大人も同じですが、食事の後に歯磨きをしないと、どうしても口の中に食べカス等が残ってしまいますよね。赤ちゃんも同様に口の中にプラークが残ってしまいます。
唾液は歯の石灰化を促すと言われています。唾液により細菌が作った酸を中和し洗い流されたり、溶け出したカルシウムやリンを歯の表面に戻す働きをしてくれるようです。
その作用を再石灰化と呼ぶようですが、唾液の分泌量が減少することで、歯の再石灰化が行われにくくなってしまいます。
添い乳により母乳が口の中に残ることで、もともと分泌量の少ない唾液が子どもの口の中に行き渡らなくなってしまうようです。
結果として、添い乳によって虫歯ができやすい状態が出来上がってしまいます。
母乳が直接的に虫歯の原因となるわけではなく、口の中に唾液が少なくなる手助けをしてしまって間接的に虫歯を作りやすくしてしまうんね。
離乳食が始まると、どうしてもこのプラークを全て取り除くというのはなかなか簡単ではないかもしれません。
子どもが思うままに歯磨きをさせてくれたらまだプラークを取り除きやすいかもしれません。ですが、実際そうならない家庭も多いのではないでしょうか?
残念ながら我が家では子どもが思うままに歯磨きをさせてくれない時期があり、泣き喚く我が子の身体を押さえながら歯磨きをしていたこともあります。
今では、歯磨きを嫌がった時にどうすれば歯磨きをしてくれるのかが分かってきたため、以前より子どもの歯磨きで悩んだりすることは少なくなりました。
では、どのようにすれば、添い乳をしながら子どもの虫歯を防ぐことができるのでしょうか?
添い乳をしながら虫歯を防ぐには?
残念ながら、添い乳をしながら虫歯を確実に防ぐ方法は無いと考えた方が良いでしょう。
あるとすれば、プラークが残らないように綺麗に歯磨きをした後に添い乳をすると、もしかしたら虫歯を防げるかもしれません。
ただ、ネット上には、添い乳をしても虫歯にならなかったママもいれば、添い乳を続けていて子どもの歯が大変になったママもいます。
ネット上のとあるママたちの体験談
子どもが虫歯になって大変な思いをしている家庭もあるんだね…
我が家では、乳児期から添い乳をずっと続けていました。それでも、娘が1歳6ヶ月検診を受けた時に虫歯はありませんでした。
ですが、歯科医の先生に尋ねてみると「虫歯になるから添い乳は止めた方が良い」と断言されました。その後、悪戦苦闘しながら歯磨きをした後の寝る前の添い乳はやめるようになりました。
虫歯を考えると添い乳は止めた方が良い、というのは間違いないようです。ただ、子どもが嫌がってなかなか添い乳をやめられない、というご家庭もあるかもしれません。
完全に虫歯を防ぐ手立てはないのかもしれませんが、我が家でどのようにして虫歯にならなかったのかをご紹介したいと思います。
添い乳でも虫歯にならなかった体験談とその方法
決して、添い乳をおすすめしている訳ではありません。どうしても添い乳をせざるを得ない状況で、虫歯にならなかった体験談です。
同じ方法をやってみても、歯の状態や口の中の環境によって虫歯になってしまうかもしれません。分かりやすいように、娘の歯の状態や日々の歯磨きの頻度、添い乳の状況などをまとめてみました。
娘の歯にまつわるステータス

- ⚫︎娘の年齢と歯の状態
-
年齢:2歳1ヶ月
乳歯の数:上歯8本下歯8本
虫歯:0本
※1歳6ヶ月検診後、歯医者さんでフッ素塗布をしてもらいました。 - ⚫︎歯磨き頻度
-
平日:朝晩2回(幼稚園通いのため)
休日:毎食後3回(家にいる日はきちんと歯磨き) - ⚫︎お菓子やジュースの頻度
-
平日:1日2回(幼稚園のおやつタイムにお菓子やジュース、フルーツ、ケーキなど)※家では不定期で、食事の時に100%フルーツジュースを飲んだり、デザートにフルーツを食べたりしています。
休日:主に乳児用のお菓子や100%フルーツジュース、フルーツを不定期で摂っています。
- ⚫︎ 添い乳のタイミングと頻度
-
明け方:1回程度
夜間に喉が乾いた時に基本はお水を飲みますが、明け方どうしてもおっぱいを欲しがる時には授乳をしています。
-
※2歳を迎えましたが、卒乳はしていません。今でもママのおっぱいが大好きなようです、最近では「おっぱいそろそろ終わりにしようかな」と言えるようになりました(笑)
添い乳をしても虫歯にならないために気をつけたこと
虫歯にならないために、次の4つのことをしました。
① 毎食後の歯磨きを欠かさない
歯磨きは毎食後必ずするようにしていました。歯磨きをするのが日中なのか、寝る前なのかで歯磨きの丁寧さにバラつきはありました。
- 日中の歯磨き
-
立たせ磨きでサッと(無理なくできそうであれば、寝かせ磨き)
- 寝る前の歯磨き
-
寝かせ磨きでしっかりと
歯磨きをする時には必ずフッ素コートを使ってするようにしていました。

このピジョンのおやすみ前のフッ素コートは、娘の歯が生え始めて歯磨きをするようになってからずっと使っています。甘味があるので、歯磨きを嫌がらずにやってくれるのにも役立っています。
また、1歳6ヶ月を過ぎてからキシリトールとフッ素が含まれているタブレットも歯磨き後のご褒美として娘に毎回あげるようにしています。

虫歯を防ぐためという側面もありますが、同時にイヤイヤ期の歯磨きをできるだけスムーズにしてくれるようにするために使っています。
歯磨きをしてくれず困っている方は、下の記事をチェックしてみてください。
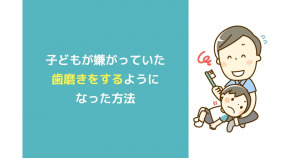
② 虫歯菌を増やさない
娘の虫歯菌を増やさないように、3つのことに気を付けていました。
1. 子どもが食べる食事には親は口をつけない
2. 子どもが使う食器は、親は使わない
3. 子どもとキスや食べ物の口移しをしない
ただ、娘は生後6ヶ月から保育園に通い、同年代のお子さん達と一緒に過ごしていたため、どの程度虫歯菌を抑えられたかは分かりません。
というのも、園での集団生活の中、他のお子さんが舐めたおもちゃなどを娘も舐めて、虫歯菌をもらってきていた可能性も否定できないからです。
③ 夜寝るときには添い乳をしない
1歳6ヶ月検診の後、夜寝るときには添い乳をしないようにしました。これは、検診で歯科医の先生に添い乳をやめた方が良いとアドバイスを受けたためです。
もちろん、その後添い乳自体をやめてしまうことができれば良かったのですが、夜間娘が起きた時の添い乳はまだやめることができずに続いています。
当時、結構大変でしたが、部屋を分かれて娘と私(パパ)で一緒に寝たり、歯磨きをした後はおっぱいもおやすみだよと娘に言い聞かせるなどして、夜寝るときには添い乳をしないようになりました。
その甲斐もあってか、添い乳を続けてきても娘の虫歯を防げている部分もあるのかもしれません。
④ 歯医者さんでフッ素塗布をしてもらった
同じく、1歳6ヶ月検診の後ですが、歯医者さんに行ってフッ素塗布をしてもらいました。
どのお子さんもやると思いますが、子どもが虫歯にならいように定期的にフッ素塗布をしてもらうことで虫歯予防につながります。
娘も検診の後、1度フッ素塗布をしてもらいました。
結果、どの方法が虫歯を防いでくれたのか、全ての方法が効果的だったのか分からない部分はありますが、添い乳を続けていても、2歳1ヶ月の娘は虫歯になっていません。
どうしても虫歯リスクは残ってしまうようなので、添い乳をやめられるのならやめるに越したことはないと考えています。
ただ、添い乳がやめられない、虫歯が心配、という方がいたら完全に虫歯を予防できる保証はありませんが、上の方法を試してみてもらえたらと思います。
知っておきたい虫歯以外の添い乳リスク
添い乳を行うママにとって、子どもが虫歯になってしまわないかどうかは、とても気になることでしょう。
ただ、虫歯以外にも気をつけておかないといけないことがあります。
特に注意をしたいのは、添い乳が原因で起こる乳児の窒息事故です。
①窒息事故死
添い乳をするうえで一番気をつけたいのが、窒息事故でしょう。
せっかく生まれてきた我が子の命を失うのは何としてでも避けたいことでしょう。
消費者庁が出している注意喚起『0歳児の就寝時の窒息死に御注意ください!』によると、平成22年から平成26年までの5年間で0歳児の就寝時の窒息死事故が160件確認されたとされています。
うち5件は、就寝時に家族の身体の一部で圧迫されたことによる死亡事故とされています。
少なくとも1年に1度の頻度で、添い乳を含む家族の身体の圧迫が原因で乳児の死亡事故が起こっていることになります。
窒息事故を防ぐだめに
では、具体的に添い寝をしながら窒息事故を防ぐためにどのようなに注意すれば良いのでしょうか。
医師の伊藤英介氏(NHK WEB特集 『“添い乳”で赤ちゃん窒息死相次ぐ 授乳に注意』)によると、添い寝の事故を防ぐために次のようなポイントに注意する必要があるようです。
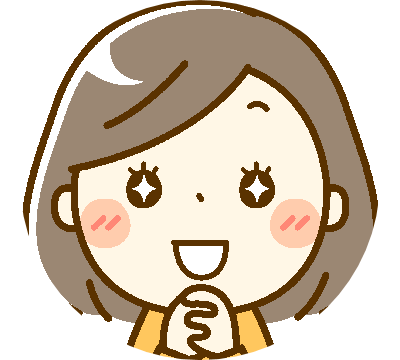
添い乳をする場合、赤ちゃんの窒息事故を防ぐために気をつけないといけませんね!
▼ 赤ちゃんと別々に寝る場合
1. ベビーベッドを利用して、赤ちゃんを一人で寝かせる
2. ミルク育児をしている場合には、夜間の授乳はパートナーに代わってもらう
▼赤ちゃんと一緒に横になる場合
3. 疲れている時に授乳をしない
4. 家族にもリスクを知らせ、定期的な見守りと母親が眠ってしまった場合の声掛けを徹底する
5. 眠気を催す薬を飲んだ後は、一緒に横にならない
▼寝具にも要注意
6. 柔らかい布団やマットはうずもれて窒息するおそれがあるので、かたいものを使う
7. 大人の掛け布団は重いので、子ども用の軽い布団を使う
NHK WEB特集 『“添い乳”で赤ちゃん窒息死相次ぐ 授乳に注意』
授乳や育児でママが疲れてしまうことは多いですよね?
そうなると添い寝時の窒息リスクも高まってしまうため、家族全員でリスクを共有し、決してママ一人だけのワンオペ育児にならないようにパパや他の家族と一緒に協力してやっていくことが大事ですね。
②頭位性中耳炎
赤ちゃんの添い乳のリスクは、窒息事故だけではありません。
添い乳で中耳炎になるって聞いたことはありますか?添い乳をすることで、頭位性中耳炎になる可能性があると言われています。
では、頭位性中耳炎とはどういったものなのでしょう?
添い乳でみんな頭位性中耳炎になるの?
では、添い乳をすると、みんながみんな頭位性中耳炎になるのでしょうか?
決して添い乳をしたからといって全ての乳幼児が頭位性中耳炎になる訳ではないようです。
どういう原因で頭位性中耳炎になるのでしょう?
国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科診療部長 守本 倫子氏(キョーリン製薬 『ミルク性中耳炎』)によると、頭位性中耳炎の原因は、逆流性食道炎のようです。
横になったような状態でミルクを飲んだことが原因というわけではなく、赤ちゃんの胃の内容物が逆流してきて、それが耳にまでいってしまったために中耳炎になると考えられているようです。
頭位性中耳炎を防ぐために
では、どうすれば、添い乳をしながら、赤ちゃんが頭位性中耳炎になるのを防ぐことができるのでしょうか?
母乳を飲ませた後に赤ちゃんを起こして抱き、ゲップを出させてあげれば、中耳炎になることを予防できると言われています。
そもそも、赤ちゃんは食道や噴門部(胃の入口、食道につながる部分)などがすごく弱く、逆流しやすいようです。
例えば、赤ちゃんはミルクを飲ませてそのまま少しほうっておくとゲボッと吐いたり、咳や泣いたりしただけで吐いてしまったりすることがありますよね?それは食道や噴門部が弱いために起こるようです。
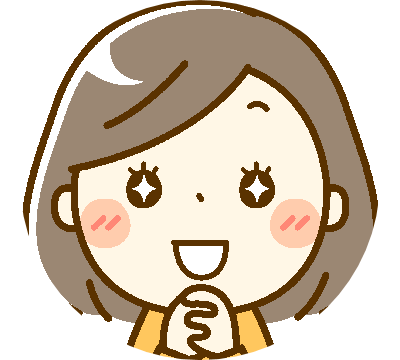
添い乳が終わった後に赤ちゃんにゲップをさせてあげることが大事なのね!
普段は縦抱きで授乳をしたり、授乳を行った後にゲップを出させてあげたりしますよね?そうすることで、胃物の逆流を防いでいるようです。
添い乳の場合、ミルクを飲んだ後にゲップをさせてあげず、横になった体勢のまま寝てしまうことが原因でこの頭位性中耳炎になってしまうようです。
③白斑
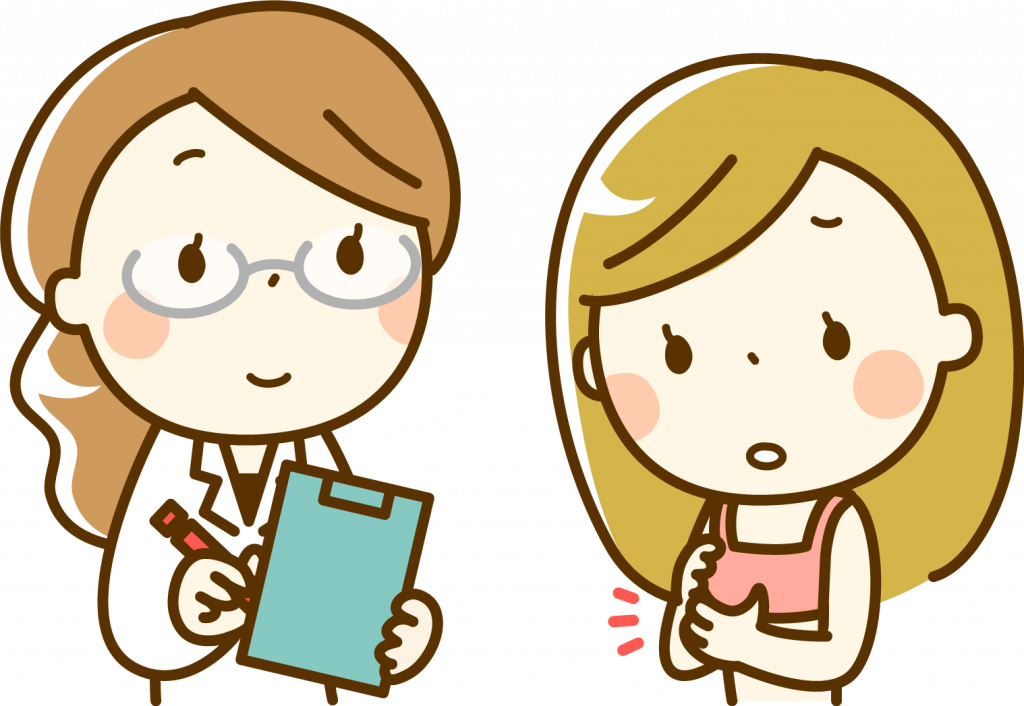
添い乳を続けることで、白斑になる可能性もあると言われます。
白斑とは、乳頭の先端に見られる直径1mm〜5mmくらいのニキビのような白い斑点(出来物)のことです。この白斑ができることを乳口炎とも言うそうです。
この白斑ができてしまうと、乳管が詰まり母乳が乳腺内にとどまり、シコリができることが多く、授乳をする時に針で刺されるような痛みを感じてしまうようです。
どうして白斑になるの?
白斑の原因とされているのは、乳首の皮膚に負担のかかる授乳と言われています。
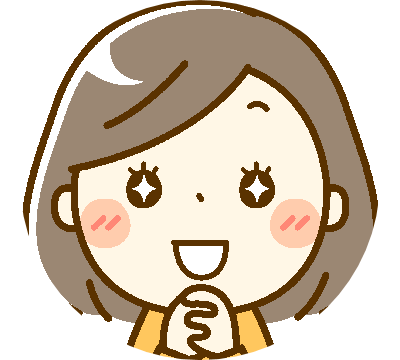
乳首の皮膚に負担がかかる授乳を続けることで、白斑ができてしまうんだね。
ではどのような授乳が、乳首の皮膚に負担をかけてしまうのでしょうか?
皮膚に負担をかけてしまう授乳の仕方が4つあると言われています。
① 赤ちゃんに乳首を長時間吸わせる
赤ちゃんに長時間乳首を吸わせることで、乳首の先の皮膚に負担がかかってしまうようです。
赤ちゃんが乳首を吸った時に乳が射出される「射乳」と呼ばれる状態が終わると母乳はほとんど出なくなり、赤ちゃんがおしゃぶりのように吸っているだけになる事が多いようです。
赤ちゃんは乳首を吸っていると安心するかもしれませんが、満足したらほどほどにして乳首を休ませてあげることも必要かもしれません。
② 頻回すぎる授乳をする
頻回すぎる授乳を行うと、乳首に負担がかかってしまうことが多いようです。これは、イメージしやすいかもしれません。
回数が多くなると、その分乳首への負担がどうしても増えてしまいますよね。
赤ちゃんが新生児の頃は、飲む力がそれほど強くないため、一回の授乳で十分な量のおっぱいを飲むことができない事が多いようです。
そのため、赤ちゃんのお腹を満たすために頻回に授乳をする必要があるようですが、限度を超えてしまうと、乳首に負担がかかってしまうようです。
③ 乳首・乳輪が固いまま吸わせる
乳首・乳輪が固いと赤ちゃんの舌が滑って深く乳首をくわえられない為、乳首の先を吸ってしまうことにつながり、ママがとても痛いだけでなく、乳首の先に負担がかかってしまうようです。
④ 乳首を浅くくわえさせる
赤ちゃんがおっぱいを吸う時に乳首のくわえ方が浅いと乳首が傷つきやすくなってしまうようです。そのため、乳輪全体を口に含ませるように乳首を深くくわえさせられるようにするのがポイントと言われています。
また、白斑にならないために下記の点にも注意が必要だと言われています。
● 授乳の間隔を空けすぎないこと
授乳の間隔が空き過ぎると、おっぱいがパンパンに張ってしまい、母乳の出がとどこおってしまうため、詰まりやすくなってしまうそうです。
また、おっぱいが張っていることで、赤ちゃんがうまく乳首をくわえることができなくなり、うまく母乳を飲み切れずに飲み残してしまう原因にもなってしまいます。
● 色々な抱き方や体勢で授乳すること
いつも同じ抱き方や体勢で授乳をしていると、乳口からの母乳の出に偏りが出て母乳がとどこおってしまう原因や母乳の飲み残しの原因となってしまうと言われています。
④乳腺炎
最後に、乳腺炎です。
添い乳をすることで、乳腺炎にもなってしまう可能性があると言われます。
乳房には、乳腺という管状の器官があり、この乳腺を通じて乳頭の先まで母乳が運ばれるようです。
この乳腺に炎症が起きた状態が乳腺炎と呼ばれます。
乳腺炎の主な症状に、下記のような症状があるようです。
● 乳腺炎の症状
◦ 乳房や胸周辺の痛み
◦ 乳房の熱感、赤み、しこり
◦ 乳房が張る、固くなる
◦ 母乳が黄色っぽい
◦ 頭痛や発熱、関節の痛みや寒気など
2つの乳腺炎とその原因
乳腺炎はその状態の違いから2つに分かれると言われています。
それは、急性うっ滞性乳腺炎(急性停滞性乳腺炎)と急性化膿性乳腺炎です。
● 急性うっ滞性乳腺炎(急性停滞性乳腺炎)
急性うっ滞性乳腺炎は乳腺に炎症を起こしている状態で、母乳が乳房にたまってしまうことが原因となって発症するようです。
● 急性化膿性乳腺炎
急性うっ滞性乳腺炎に細菌感染をともなってしまうと急性化膿性乳腺炎になってしまうと言われています。
急性うっ滞性乳腺炎で乳腺に母乳がたまっている場合、その状態が半日から1日以上続くと母乳が細菌感染して化膿することもあるため、すぐに近くの病院を受診し適切な治療やケアを受けた方が良いようです。
乳腺炎は、白斑と同じで、同じ授乳姿勢を続けていると決まった乳腺からしか母乳が吸われなくなって発症してしまうようです。古い母乳が溜まった乳腺では、しこりや乳腺炎が起こりやすくなってしまうようなので、もし添い乳を行う時は、注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。
できることなら添い乳をやめられるに越したことはないでしょう。
ただ、もし添い乳を続けざるをえない状況で、子どもを虫歯にはしたくないというご家庭があれば、我が家の体験談を参考にしてもらえると嬉しいです。

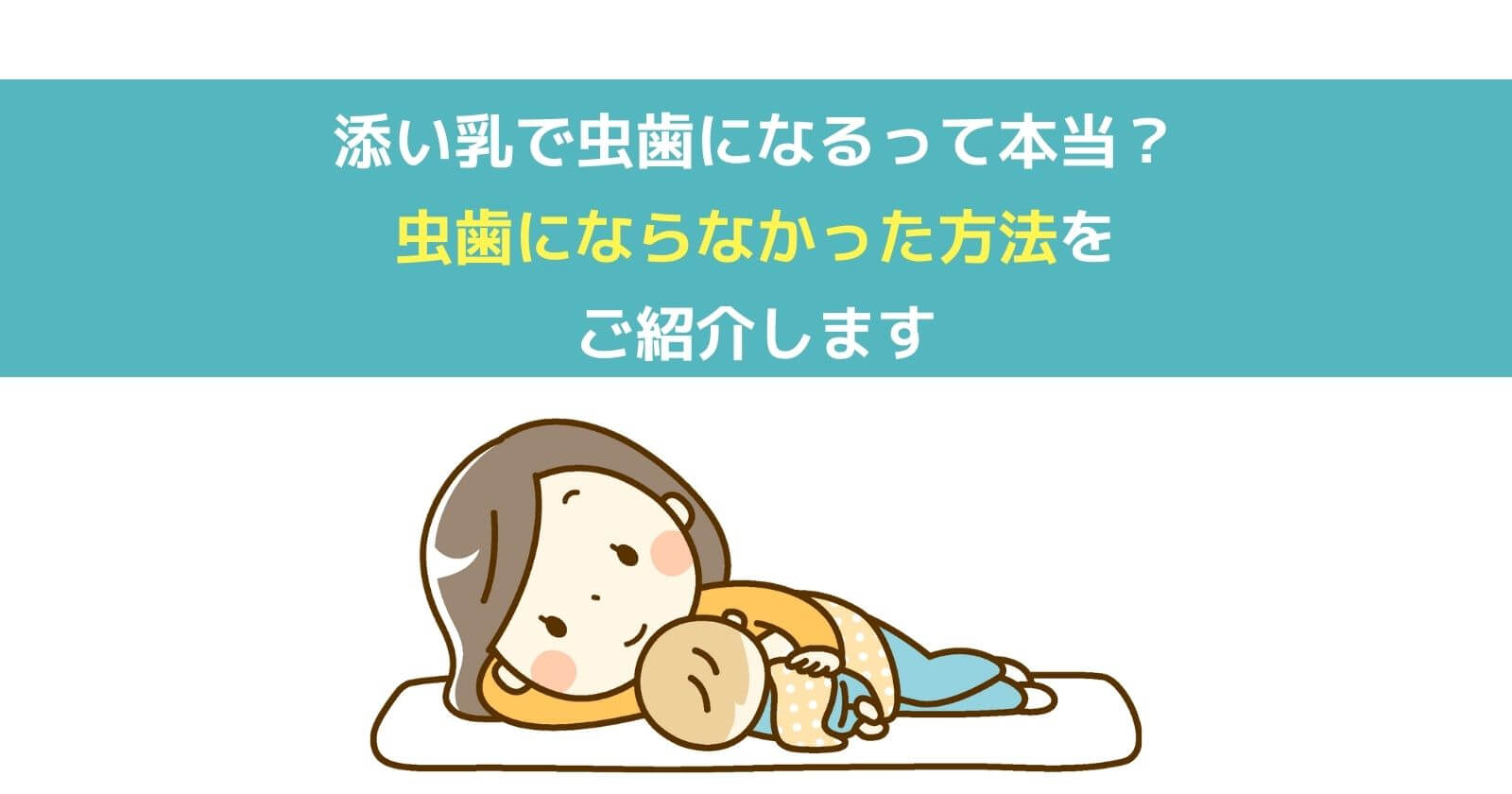
コメント